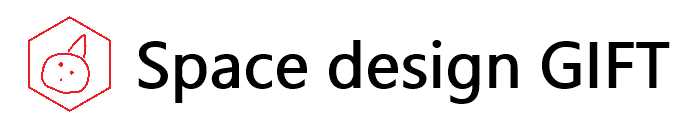1秒の長さを再定義
もうすぐ秋分の日。1日の昼と夜の長さがほぼ同じになる日ですね。
先日、日経新聞に1秒の長さが2030年に再定義される予定との記事がありました。
国際度量衡委員会にて再定義の手段が議論され、東京大学の香取教授が発明した「光格子時計」が有力視されているそうです。
今までの定義は何だったのだろう?と調べたところ、
1.地球の自転に基づく秒(19世紀まで)
・「1日を24時間、1時間を60分、1分を60秒に分けたときの1秒」とされ、地球の自転に依存していた。しかし、地球の自転は潮汐摩擦や地殻変動の影響で正確さに限界があった。
2.地球の公転に基づく秒(1956年~1967年)
・自転が不安定なため、より安定している地球の公転を基準にした。しかし、これも観測に依存するため限界があった。
3.原子時計による秒(1967年~現在)
・現在の国際的な定義は「セシウム133原子の基底状態にある2つの超微細準位に遷移に対応する放射の9,192631,770周期の継続時間を1秒とする」これは原子時計で実現され、非常に安定かつ再現可能である。(む、難しい定義だ・・・)
つまり、日常生活で体験できる秒の長さは変わらないが、現在はセシウム原子を基準にしており、さらに精度が高い光格子時計(ストロンチウムやイッテルビウムなどを使った光時計)が次世代の定義候補となっているということです。
光格子時計が導入されると科学研究の正確さがますます向上していきそうですね。
5年後の再定義が楽しみです!